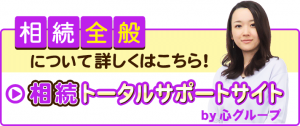相続土地国庫帰属制度
国庫帰属制度の不承認事由について
皆様、お久しぶりです。弁護士の林です。
今回は、相続土地国庫帰属制度の「不承認事由」について解説していきたいと思います。
1 不承認事由一覧
⑴ 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑵ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑶ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑷ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑸ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
以下、解説していきます。
2 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
勾配30度以上+高さ5メートル以上に該当する崖がある土地であって、通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地は国庫帰属することができません。
この時の「通常の管理に過分な費用・労力がかかる」か否かの判断は、住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが挙げられています。
3 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
①工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する土地であって、かつ、②その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する場合には国庫帰属をすることができません。
具体的な例でいくと、果樹園の樹木や倒木、定期的な伐採が必要とされる樹木が挙げられます。
4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
以下の土地に該当する場合には、申請が認められません。
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)
② 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
③ 所有者以外の第三者によって占有されている等、使用収益が阻害されている土地
5 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
① 災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
② 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
③ 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
④ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
⑤ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
以上です。
次回からは、また新しいテーマについて解説しようと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
国庫帰属制度の添付書類について
皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
前回に引き続き国庫帰属制度についての解説を行っていきます。
今回のテーマは「添付書類について」です。
1 提出書類
国庫帰属制度の申請を行う場合には、管轄法務局に対して書類を提出していく必要があります。
提出書類は以下のとおりです。
① 承認申請書
② 承認申請書に記名押印した人の印鑑証明書
③(対象の土地の名義変更をしていないとき)承認申請者が所有者または共有者であ
ることを示す書類
④ 対象の土地の位置及び範囲を明らかにする図面
⑤ 対象の土地の形状を明らかにする写真
⑥ 対象の土地と隣接する土地の境界点を明らかにする写真
⑦ 申請が承認された時に所有権移転登記がされることを承諾したことを証する書面
2 解説
⑴ 承認申請書
ア 必要事項
承認申請書には、以下の事項を記入し、申請者または法定代理人が記名押印する必要があるとされています。
① 承認申請者の名前
② 承認申請に関わる土地の所在、地番、地目及び地積
③ 承認申請に係る土地の「表題部所有者」または「所有権の登記名義人」の氏名
及び住所
イ 調査方法と根拠資料
上記の情報を記載する場合には、対象不動産の管轄法務局に行き、「登記簿謄本」を取得することで正確な情報を得ることができます。
登記簿謄本の取り方については、法務局のこちらのホームページが参考になります。
登記簿謄本の取得の際には、窓口に行く以外にも、郵送やオンライン請求が可能ですので試してみるのも良いかもしれません。
⑵ 承認申請書に記名押印した人の印鑑証明書
承認申請者の印鑑証明書の提出が必要とされているのは、本当に承認申請者が「国庫帰属制度」を利用したいという意思を持っているかを判断するためです。
⑶ (対象の土地の名義変更をしていないとき)承認申請者が所有者または共有者であ
ることを示す書類
具体的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」や、「遺産分割協議書」が該当します(戸籍謄本はお近くの市役所で取得できるようになりましたので一度確認してみるのも良いかもしれません(戸籍謄本の広域交付制度)。)。
例えば、お亡くなりになった父親の土地について相続開始後すぐに国庫帰属したいと考えた場合について見ていきましょう。
この時、お父様がお亡くなりになったばかりなので、登記簿に記載されている所有者は「お父様」です。
お父様は既に亡くなっていますので実質的な所有者は相続人となりますが、登記簿の名義変更を行うには「相続登記」を行う必要があり、登録免許税や専門家報酬がかかってしまいます。
そのため、実質的な所有者や共有者がが明らかな時には「相続登記」をしなくて良いことになっているのです。
⑷ 対象の土地の位置及び範囲を明らかにする図面
具体的には、登記所に備え付けられている地図の写し(14条地図や公図)や国土地理院が公開している地理院地図などに申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したものが必要となります。
⑸ 対象の土地の形状を明らかにする写真
具体的には、対象地の全体を撮影した写真で、⑷の位置関係と範囲が分かるように撮影された写真である必要があります。
これは、国庫帰属制度の対象地が現在どのような状態なのかを確認するために必要とされている写真です。
⑹ 対象の土地と隣接する土地の境界点を明らかにする写真
具体的には、境界標やブロック塀、道路のへりなどの簡単に分かる目印となるものであればよいとされています。
上記⑷の図面に示された範囲等が分からない場合には、適正な写真とは認められないので注意が必要です。
⑺ 申請が承認された時に所有権移転登記がされることを承諾したことを証する書面
国庫帰属を承認する判断がされた場合には、所有権が国に移ることになりますので、その登記を行うことを承諾する書面の提出が必要になります。
このように、国庫帰属制度の申請に当たっては、必要となる書類が多いですので、難しい場合には、専門家に相談されるのが良いでしょう。
それでは、また次回お会いしましょう。
次回は、「国庫帰属制度の不承認事由」について解説していく予定です。
国庫帰属制度の申請手続きについて
皆様、お久しぶりです!
弁護士法人心の林です。
前回は、国庫帰属制度の利用状況等について解説してきました。
今回は、それに引き続き、国庫帰属制度の申請手続きの流れについて解説していきたいと思います。
国庫帰属制度の大まかな流れは、以下のとおりです。
① 申請者を選定する
② 添付書面を準備する
③ 法務局における内部審査
④ 審査結果の通知又は取下げ
⑤ 負担金の納付
以下解説していきます。
1 申請者を選定する
⑴ 原則
国庫帰属制度の申請者としては、基本的には相続等によりその土地を取得した者と考えられています。
そのため、売買契約や贈与契約によって所有権を取得した人は原則として国庫帰属制度を利用できないという点については、注意が必要です!
また、手続きが煩雑なので代理人に申請手続きを任せたいというご希望をお持ちの方もいらっしゃいますが、任意代理人(弁護士や司法書士等の専門家)は申請者となることができないとされていることに注意が必要です(法定代理人(父母や成年後見人等)は申請の代理まで行えます。)。
もっとも、申請書類の作成代行を行うことまでは禁止されていないので、不安な方は経験豊富な専門家に申請書類の作成代行を依頼するのが良いでしょう。
⑵ 例外
ア 共有者がいる場合
国庫帰属制度は土地の所有権を国に移転させるという制度ですので、共有者が居る場合には、他の共有者全員を含めて申請することが必要とされています。
そのため、一人でも国庫帰属に反対をしている方が居る場合には、申請自体ができないということになります。
イ 法人の場合
法人は相続等によって土地を取得することは通常考えられないため、原則として国庫帰属制度の申請者となることはできないと考えられています。
もっとも、法人が共有者として登記されている場合に、他の自然人が相続等により土地を取得した場合には、法人も申請主体となることができるとされています。
このような場合には、自然人までも申請を妨げられることになってしまうという結果を避けるための措置がしかれているという事になります。
2 添付書面を準備する
添付書面については、少し複雑なので、次回に解説を行います。
3 法務局における内部審査
⑴ 管轄法務局
国庫帰属制度の管轄法務局は、各土地が所在する場所を管轄する法務局とされています。
もっとも、支局や出張所は管轄法務局となることはできず、それぞれの所在地を管轄する法務局の本局に管轄があるとされています。
例えば、岐阜の高山にある土地については、通常は岐阜地方法務局の高山支部に不動産登記の申請を行いますが、国庫帰属制度の申立ての場合には、岐阜地方法務局の本局に申立てを行う必要があるという事です。
⑵ 標準処理期間
国庫帰属制度の申請を許可するか否かについて、法務局は平均して8カ月程度で審査結果を伝えるとの運用を行っています。
これは、申請された土地の現在の状況や、国家による有効利用の可能性等を検討するために設けられている期間であり、それを審査するのに、おおよそ8か月かかるという事を示しています。
4 審査結果の通知又は取下げ
法務局は、申請から約8か月後に国庫帰属を認めるか否かの通知を行います。
その際に法務局が行う判断の内容は以下のとおりです。
「取下げ」は法務局が行う判断ではないですが、申請手続きが終了するという意味で同一ですので、並行して説明を行います。
⑴ 承認
法務局は、国庫帰属の申請を承認することとした場合には、申請者に対して、承認したことを通知します。
この承認の通知は後で説明する、「負担金の納付」の通知と併せて行うこととされています。
⑵ 却下
法務局は、次のいずれかの事由に該当する場合には、申請を却下することができるとされています。
ア 申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき
イ 承認申請者が必要事項を記載した承認申請書を提出しないとき
ウ 審査手数料を納付しないとき
エ 正当な理由がないのに、法務大臣の事実の調査に応じない時
この時の却下とは、申請権者ではない等の形式的要件を欠いている場合を指しており、後述する「不承認」とは異なる判断結果ですので、注意が必要です。
上記のような事由があると、そもそも審査すらできないため、必ずこの点の確認は行うようにしましょう。
⑶ 不承認
法務局は不承認事由がある場合には、申請を不承認とすることができるとされています。
(不承認事由については、次回以降に詳しく解説します。)
この不承認に対しては、行政不服審査や行政訴訟を行うことができるとされていますので、問題があると考えるときは不服を申し立てるのもありかもしれません。
⑷ 取下げ
申請自体は取り下げる事ができます。
ただこの時でも、審査手数料は帰ってこないため、注意が必要です。
5 負担金の納付
国庫帰属の申請が承認されたときは、負担金を納める必要があります。
この負担金は、基本的には一筆について20万円とされることが多いようですが、当該土地を管理するのに、草刈り等の管理が必要となる場合には、面積に応じた金額の納付が必要となるとされています。
そのため、広大な土地を国庫帰属させるには、それに対応できるだけの現金が必要になりますので、注意が必要です。
今回は、国庫帰属制度の大まかな申請手続きの流れについて解説していきました。
次回は、添付書類及び不承認事由について解説していきたいと思います。
それでは、また次回お会いしましょう。
国庫帰属制度の概要について
皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
今回からは、令和5年から始まった「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていきたいと思います。
1 制度趣旨
「相続土地国庫帰属制度」は、土地を相続により取得した場合に、一定の要件に該当する場合には、その所有権を国に帰属させることを認める制度になります。
この制度ができた背景としては、人口の都市部への集中を契機として、自身にとって不要な土地を相続することへの負担(固定資産税や管理費等の諸費用)が、所有者不明土地の拡大の一端を担っているという指摘を受け、それを解消するために所有者に任意に所有権を放棄することを認めたという点にあります。
2 現在までの運用状況
令和5年の運用開始から令和7年1月31日までの速報値に基づく統計を参照(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html)してみます。
⑴ 申請件数
申請件数の推移としては、現在までに「3343」件の申請が行われています。
運用開始から1年半と少しの期間に3000件以上の申請がなされていることからして、不要な土地を手放したいというニーズは今後も増えていくことが予想されます。
また土地の属性ごとの分類では、「宅地」が1188件、「田畑」が1258件「山林」が520件とされています。
⑵ 帰属件数
これに対して、実際に所有権が国に帰属した件数としては、全体で「1324」件となっており、約39%の割合で申請が認められている計算になります。
また土地の属性ごとの分類では、「宅地」が518件、「田畑」が405件、「山林」が63件とされています。
この値から、「宅地」は約43%、「田畑」が約32%、「山林」が約12%の割合で認められていることが分かります。
このことから、一番需要が高いと思われる山林の所有権帰属には、高いハードルがあることが推察されます。
3 申請前の相談の活用
現状の運用状況の評価としてはこのような状況ですが、申請前にどの程度の割合でご自身の申請が認められるかを推察することができる方法があります。
それが、法務局の相談窓口の活用です。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html)
法務局では、完全予約制で手放したい土地の国庫帰属に関する申請の相談を受け付ける事とされています。
この相談では、一般的な質問にとどまらず、申請を行った場合の見通しや、申請書類の不備の確認など、個別具体的な相談にも乗ることができるとされています。
そのため、実際に申請を行う前には、必ず法務局への相談を行った方が、より正確な見通しを立てられるようになるといえるでしょう。
以上です。
今回は、「相続土地国庫帰属制度」について、制度趣旨の説明と現状についてお話をしてきました。
次回は、実際に「相続土地国庫帰属制度」の申請手続きのご説明や添付書類の解説を行っていきたいと思います(内容によっては、二回に分ける可能性もあります。)。
それでは、また今度お会いしましょう。
- 1