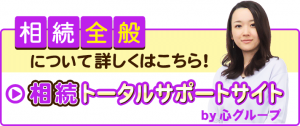- トップ
- ブログ
ブログ
認知請求と放棄を約束する契約の有効性
皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
まだまだ暑い日が続きますね。
本日は、認知請求と認知請求を放棄する契約の有効性についてお話していきたいと思います。
1 認知請求とは、父親が子供との法律上の親子関係を認めない場合に、子が父親に対して法的父子関係を認めるように請求する権利のことを指します。
この時、父親としては、法的親子関係を認められてしまうと、養育費の支払い義務や、相続権が発生してしまうので、それらを回避するために認知請求を避けたいと考える場合があります。
その方法として、いくらかの金銭を子供や母親に渡して、認知請求権を放棄してもらう契約を行うという場合があります。
このような契約は、そもそも契約として有効なのでしょうか。
2 この点について、判例・通説は、このような契約は無効であると考えています。
根拠としては、父との父子関係が認められることが、基本的に子供の利益となる点や、このような契約を認めると少ない金額で放棄の契約がされてしまうおそれがあって子供の利益に適合しないという点が挙げられています。
もっとも、子供の利益を十分に確保した場合には有効となるという考え方もあるので、これからの裁判例に注目する必要があるでしょう。
3 では、既に放棄の契約を行っていた場合には、どのようになってしまうのでしょうか。
例えば、父から多少のお金を渡されて契約書に押印を行っていた場合にはどのような処理となるのでしょう。
この場合、子供としては、父親に対して、認知請求を提起することができます。
上述のとおり、認知請求の放棄をする契約は無効であるため、当然の帰結といえるでしょう。
では、契約の際に支払った金銭については、どのように処理するのでしょうか。
この処理方法の一つとして、父親から子供に対して不当利得返還請求として、支払った金額の返還を求めるという解決が考えられます。
もっとも、このような不当利得返還請求については、「父子関係を認めない」という信義則上許されない原因で渡したお金なので、返還が認められないという考え方や、養育費の一部として理解して返還を認めないという考え方があるため、注意をしましょう。
4 このように、認知請求を放棄する契約に関しては、様々な考え方が指摘されているところです。
そのため、少しでも疑問に思ったことがある場合には、お近くの弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
それでは、また次回お会いしましょう。
遺言書で生命保険金の受取人を変更する方法と裁判例
お久しぶりです。
弁護士法人心、弁護士の林です。
皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
私は、先日、豊田の鞍ヶ池公園までドライブに行きましたが、暑すぎたので早々に帰宅してしまいました。(笑)
さて、今回は、生命保険の受取人を遺言書で変更する方法とその記載方法について、解説していきたいと思います。
1 原則
まず、そもそも保険金の受取人を遺言書で変更することは可能なのでしょうか。
この点、保険法44条1項は、
「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」
と規定しています。
そのため、遺言書によって保険金の受取人を変更することは可能なのです。
但し、同条2項は、
「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」
と定めています。
この規定により、例え遺言書で受取人の変更を行ったとしても、保険会社が先に元の受取人に保険金を支払っていた場合には、保険会社に対して責任追及を行っていくことはできないということになります。
相続人の方は、この規定に注意を払って、なるべく早期に行動するように心がけることが重要でしょう。
2 遺言書の記載方法
では、遺言書で受取人の変更を行う場合には、どのような記載方法を取ればよいのでしょうか。
ここでは、一般的に推奨される方法と裁判例から見る傾向を見ていきましょう。
ア 一般的に推奨される記載例
一般的に、遺言書で保険金の受取人を変更する場合には、できる限り以下の要素ごとに特定して記載することが望ましいとされています。
①証券番号
②保険会社名
③契約締結日
④保険契約者
⑤被保険者
⑥受取人
この6つの要素で、なるべくどの生命保険の受取人を変更するのかについて疑義が入らないようにすることが重要であるとされています。
このことから、記載としては、
「遺言者は、下記に記載する生命保険契約の受取人をAからBに変更する。
記
①証券番号 ○○-○○-○○
②保険会社名 ABC生命保険
③契約締結日 令和6年8月20日
④保険契約者 遺言者
⑤被保険者 遺言者
⑥受取人 遺言者の妻・A 」
等と記載するのが良いでしょう。
イ 裁判例
もっとも、必ずこの記載方法でないと受取人の変更が認められないというものではありません。
なぜなら、上記の保険法では、遺言書の書き方について法定されているわけではなく、遺言書は本来、その記載文言から、遺言者の意思を解釈していくことができるからです(「遺言書の形式的な記載だけでなく、遺言者の状況等からその真意を探求していくべきである」とした判例として、最判昭和58年3月18日があります。)。
そして、裁判例でも、生命保険の契約者兼被保険者である遺言者が「一切の財産をAに相続又は遺贈する」(原文と相違がある可能性があります。)という趣旨の遺言書を残した事案で、この遺言書から生命保険の受取人を変更することを認めた裁判例(京都地判平成18年7月18日)があります。
この裁判例では、形式的に受取人となるのは遺言者の子供でしたが、遺言者が遺言書を作成した当時、遺言者と子供は疎遠であり、電話や訪問を受けていなかったこと、遺言者が遺言書を作成したのはAの自宅で療養を受けた恩義に報いる趣旨であったことから、遺言者の意思としては、保険金を含む全ての財産をAに渡す意思であったとされたのです。
ウ まとめ
このように、生命保険金の受取人の変更に関して遺言書を記載する場合には、なるべく特定して書くことが望ましいものの、形式的に変更の意思が書かれていなくても、実質的に変更を認める余地があります。
そのため、保険金の受取人について疑義がある場合には、弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
生命保険金の受取人について
皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の弁護士の林です。
最近は、気温が高く寝苦しいですね。
皆様も体調にはお気を付けください。
今回は、生命保険の受取人が、被保険者の死亡以前に死亡していた場合の生命保険の受取人について解説していきたいと思います。
まず、生命保険契約を締結した際の受取人は、基本的に「戸籍上の配偶者又は2親等以内の親族」とされていることが多いです。
このように受取人が限定されている趣旨は、生命保険が、残された親族の生活を守っていくためのものである点にあります。
では、この時に受取人が被保険者より先に死亡していた場合には、誰が受取人となるのでしょうか。
この点について、保険法46条では、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」とされています。
例えば、被保険者と配偶者の間に子A、B、Cの3人がいる場合に、Aが受取人と指定されていたが、Aが先に死亡し、被保険者がその後に亡くなったという事案について考えてみます。
この時、Aに配偶者と子供がいる場合には、Aの配偶者と子供がAの法定相続人となりますので、Aの配偶者と子供が生命保険の受取人となります。
さらに、Aには配偶者しかいない場合には、Aの法定相続人はAの配偶者と被相続人の配偶者となりますので、Aの配偶者と被相続人の配偶者が受取人となるのです。
このように、生命保険金の受取人が先に死亡してしまった場合には、意図していない方に生命保険金が渡ってしまうことがあります。
では、意図していない方に生命保険金が渡らないようにするための方法は無いのでしょうか。
この点、一つの方法として、遺言書で受取人の変更を指定しておくという方法が考えられます。
まず、保険法44条1項にて「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」とされています。
この規定を使用し、遺言書にて「保険金受取人が被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、遺言者を被保険者とする下記の生命保険の受取人を、○○から○○に変更する。」と定めておくことで、意図していない方に生命保険金が渡らないようにすることができます。
例えば、上記の事例では、生命保険の受取人Aが先に死亡していた場合には、その受取人をBに変更すると指定することで、意図していない方に保険金が渡らないようにすることができます。
そのため、生命保険契約を結ばれている場合には、受取人の対策として遺言書を使用することも検討しておくと良いでしょう。
但し、この方法を使用する際には、
①受取人となる人に、被相続人が死亡した際には、受取人の変更を生命保険会社に通知する必要があること(保険法44条2項)を事前に知らせておくこと
②変更先となる受取人が生命保険契約の受取人として指定できる範囲内であるかを生命保険会社に確認しておくこと
を忘れずに行ってください。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
預貯金の取引履歴の取得と
お久しぶりです。
弁護士の林です。
皆様はいかが過ごされていますでしょうか。
今回は、銀行が預貯金口座の取引履歴の開示請求に対して拒否することができるのかという点について解説していきたいと思います。
相続の事案では、被相続人の預貯金口座から相続人の一人が多額の出金をしているという場合があります。
その場合、他の相続人としては、預貯金の管理状況を把握するために、預貯金口座の取引履歴を取得する必要があります。
この時、金融機関は、被相続人のプライバシーを侵害するから取引履歴を開示しないという回答をすることが許されるのでしょうか。
平成21年1月22日最高裁判例は結論として、金融機関は原則として取引履歴を開示しなければならないと判断しました。
これは、
① 預金者は、金融機関の事務処理が適切になされていることを確認するために取引履歴の開示を求める事が必要不可欠であること
② 取引履歴の開示の相手方が共同相続人である限り、プライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務違反が問われることは無いこと
の2点を理由としているみたいです。
ただし、取引履歴の開示が「開示請求の態様、開示を求める対象ないし範囲等によっては、預金口座の取引履歴の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合がある」と判断されている点に注意が必要です。
例えば、金融機関に対して預貯金口座の取引履歴を30年分開示しろという請求を想定しているものと考えられます。
上記の例との関係でいえば、被相続人の口座から多額の引き出しがあったとしても、被相続人が預貯金通帳を管理できなくなったのが5年前くらいからであるのであれば、その期間に対応した取引履歴を取得するべきであるということです。
必要以上の取引履歴の取得については、金融機関も拒否することができる場合があり得るのかもしれません。
以上より、皆様も、取引履歴の取得を拒否された場合には、諦める前に弁護士に相談してみるのが良いかもしれません。
特別受益財産の評価方法について
お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
本日は、特別受益財産の評価方法について解説していきたいと思います。
まず、特別受益とは、被相続人の生前に、被相続人が相続人に対して贈与した財産を、遺産に持ち戻して当事者間の公平をはかる制度をいいます。
この特別受益が、存在していると認められる場合、その財産の評価額はいくらになるのでしょうか?
例えば、被相続人が相続人に対して1000万円の家(被相続人の死亡時の評価額500万円、遺産分割時の評価額300万円)を贈与していた場合、特別受益も1000万円と評価されるのでしょうか?
結論として、実務では「被相続人の死亡時の評価額」を特別受益財産の評価額とすることが一般的となっております。
なぜなら、特別受益を認めた条文(民法903条、904条)により忠実である点や、渡された財産による相続開始時までの利益と損失は被相続人に負担させるのが公平である点から、そのように考えられているのです。
そのため、上記の例では、家の評価額は原則として、500万円となります。
しかし、これと異なった考え方も存在しており、その説では、「建物の価格が、経年劣化により贈与時の価格を下回った場合には、贈与時の価格を相続開始時の価格とするべきである」とされています。
この根拠は、受贈者は少なくとも贈与開始時の価格を取得していると認められる点にあります。
この考え方では、上述の例では、1000万円が特別受益に当たると考えられます。
皆様は、どちらの考え方が特別受益の評価方法として適切だと考えられるでしょうか。
弁護士としての観点からすると、依頼人により有利な考え方に基づいて両説を使い分けていけたら良いなと考えております。
それでは、また次回お会いしましょう。
異母兄弟がいる場合の相続について
天候も暖かくなってきており、名古屋でも春の到来を感じる今日この頃ですね。
本日は、異父異母兄弟の相続について解説していきたいと思います。
今の日本の法律では、基本的に嫡出子も非嫡出子も関係なく父親の遺産は均等に配分されることとなっています。
そのため、異父異母兄弟がいる場合であって、既に被相続人と疎遠になっていたとしても、親の相続の際には、異父異母兄弟にも当然に相続権が認められるのです。
しかし、異父異母兄弟の相続分が、法定相続分からさらに2分の1とされる場合があります。
それは、兄弟姉妹が亡くなった際の異父異母兄弟の相続分です。
例えば、父親は前妻との間に子Aがおり、その後再婚して後妻との間にBとCが生まれたとします。
その後、父親と後妻が亡くなり、Bが結婚をしないでなくなった際には、法定相続人はAとCになります。
その際、通常の兄弟姉妹であれば、Bの遺産を2分の1ずつ相続しますが、異父異母兄弟の場合には2分の1について、さらに2分の1を乗じて得た部分が法定相続分となるのです。
したがって、Aの法定相続分は4分の1、Cの法定相続分は4分の3となるのです。
このように、日本の法律では原則として同順位の相続人は同一の法定相続分で分けることとされていますが、例外的に異父異母兄弟の場合には法定相続分の格差が生じるのです。
このように、異父異母兄弟にも法定相続分が認められているという点にも注意して相続対策をしていきましょう。
それではまた次回お会いしましょう。
遺留分侵害額請求権が行使される可能性がある場合の遺言書
暖かな日が多くなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
本日は、相続放棄と特定遺贈について解説していきたいと思います。
1 特定遺贈と包括遺贈の違い
まず、特定遺贈とは、遺言者が、自身が死亡した際に、特定の財産を相続人又は第三者に対して渡すことを内容とする法律行為です。
この対立概念の包括遺贈は、遺言者が、自身が死亡した際に、特定の財産ではなく、財産の割合を示して相続人又は第三者に対して渡すことを内容とする法律行為です。
両者の違いは、遺言者の債務を承継するか否かという点にあります。
すなわち、特定遺贈の場合は、原則として特定された財産のみを取得し、債務を承継しないということが可能となっているのです。
反対に、包括遺贈の場合には、承継する遺産の割合にしたがって債務を承継することとされています。
2 特定遺贈と相続放棄
では、多額の債務を有する遺言者がプラスの財産のみを相続人に特定遺贈し、相続人は、特定遺贈された財産のみを承継し、マイナスの財産を相続放棄することは可能なのでしょうか。
結論からすると、マイナスの財産を相続放棄することは原則としてできないと考えるべきです。
なぜなら、類似の事例で、被相続人の財産を債務者である妻が一切相続せず、債務者でない子供が一切の財産を相続することを内容とする遺産分割協議が行われた際、その遺産分割協議が詐害行為に当たるとして取消された事例があるからです。
この事例では、プラスの財産を特定の相続人に寄せて、財産を保護しようとする考え方に対して厳しい評価が下されたと評価することができます。
したがって、裁判所はマイナスの財産のみを相続放棄することについても否定的評価を下す可能性が高いと考えるべきです。
3 まとめ
以上のように、特定遺贈を使用して、債務の承継を行わないようにするのは難しいことが分かりました。
債務の承継と相続対策を同時に行うことはかなり難しい問題となりますが、事前に債務整理等の方法で対策をとっていくのが良いのではないでしょうか。
債務整理については、お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
成年後見人の選任申し立てと鑑定手続き
寒暖差の激しい季節が続きますが、どのようにお過ごしでしょうか。
お久しぶりです、弁護士の林です。
本日は、成年後見人の申し立て手続きとその注意点について話していきたいと思います。
1 成年後見人の申し立て手続きの全体像
成年後見人の申立て手続きの全体像は以下のとおりです。
①申請書類の提出
②即日面接
③鑑定
④親族への意向確認
⑤選任
これらの手続きの中でも、慎重に対応しなければならない点は、①申請書類の提出で添付する医師の診断書③鑑定手続きです。
2 ③鑑定
成年後見人の申し立てを行う際、裁判所は成年後見人を必要とする方の認知能力等の状態を確認する手続きとして、「鑑定」を行う事が認められています。
この鑑定の結論によっては、後見ではなく、保佐人や補助人が選任される可能性があります。
保佐人や補助人は成年後見人よりも権限が狭いため、包括的にサポートを行いたいのであれば、成年後見人の選任を目指すのが合理的といえます。
そのため、成年後見人を選任してもらう確率を高くする方法を考える必要があるのです。
その方法の一つとして、医師の診断書を詳しく書いてもらい、鑑定手続きの省略を目指す方法があります。
以下、医師の診断書の作成について詳述します。
3 ① 医師の診断書
申請書類で医師の診断書が要求される趣旨は、成年後見人を必要とする方の判断能力を確認するための資料にする点にあります。
そのため、この医師の診断書に記載されている内容によっては、上記③鑑定手続きを省略する事ができる場合があるのです。
では、③鑑定手続きを省略できる診断書とは、どのような診断書なのでしょうか。
それは、「明らかに鑑定の必要がないと認められる」内容を含んだ診断書を指します。
具体的には、診断書の病名が、
①脳血管性認知症
②アルツハイマー型認知症
③遷延性意識障害(いわゆる植物状態)
④重度の知的障害
⑤脳出血後遺症
⑥脳梗塞後遺症
等に該当する場合には、「明らかに鑑定の必要がないと認められるとき」に該当するとされる事が多いようです。
さらに、その病名を診断するにあたって、長谷川式認知症スケールやMMSE等の、定型的な審査項目を記載していくタイプの診断書を添付すれば鑑定省略される可能性が高まります。
以上の事から、主治医に診断書の記載をお願いする際に、判断が難しい項目について、多少重めに記載してもらえるよう頼む事が合理的ですので、忘れずに伝えておきましょう。
4 まとめ
今回は成年後見に関して、医師の診断書と鑑定の省略について、確実に成年後見人を選任してもらうには、
① 鑑定の省略を狙う
② 鑑定の省略には医師の診断書の記載に注意する必要がある
この2点に注力する必要があることを書きました。
5 おわりに
寒暖差が激しい日が続きますが、皆様体調にお気をつけてお過ごしください。
自筆証書遺言保管制度の活用法について
皆様初めまして、弁護士法人心所属の弁護士の林唯です。
私は、事務所内で相続分野を専門的に担当する弁護士として活動しております。
このブログでは、相続分野の法的な制度や、権利等について解説していきますので、宜しくお願いいたします。
本日のテーマは、「自筆証書遺言保管制度の活用法について」です。
自筆証書遺言を作成した際、自宅に遺言書を保管しておくことで、遺言書が無くなってしまうことがあるのではないかという心配をなされる方がいらっしゃいます。
その際に、活用できるのが「法務局」に自筆証書遺言を保管できる制度です。
この制度では、法務局に自筆証書遺言を預ける際に、一人の人物を指定して、自身の死亡届が提出された際に指定した人に通知が行くように設定することができます(これを「指定者通知」とよびます。)。
この指定者通知には、さまざまな活用法があります。
例えば、2人の息子がいて、自身の相続人となる場合について考えてみましょう。
この内、一人(以下「A」)が重度の難病にかかっており、遺産を残して面倒を見てほしいが、もう一人の相続人(以下「B」)が遺産を散財する可能性があるとしましょう。
このような場合に、一つの解決策として、遺言執行者を弁護士等の第三者に指定して、指定者通知をその弁護士に指定しておくことで対策をとることができます。
実際に、遺言者様がお亡くなりになった際に、死亡届が役所に提出された段階で、役所から法務局に対して遺言者様死亡の報告がなされます。
そうすると、法務局は弁護士等に対して指定者通知を行うことになるので、弁護士等はすぐさま遺言執行者として口座の凍結、分配を開始することができます。
この方法によって、Bの散財を防ぐのと同時に、Aに必要な財産の確保を行う事ができるわけです。
その後、遺言執行者となった弁護士等は、遺言者様が後見人や訪問医療サービス等の事前に契約しておいた会社に対して、Aさんの看護を委託して任務を終了させることができます。
この例からわかる通り、相続人の中に不安な行動をとる恐れがある方がおり、かつ、他の相続人ではそれに対処できる可能性が低い場合には、「法務局」による「指定者通知」の制度をうまく活用することができます。
なお、公正証書遺言にはこのような通知の制度がないことから、「指定者通知」が法務局における遺言書保管の特徴的なメリットと考えてもいいでしょう。
以上が、「自筆証書遺言保管制度の活用法について」です。
それでは、次回のブログでまたお会いしましょう。